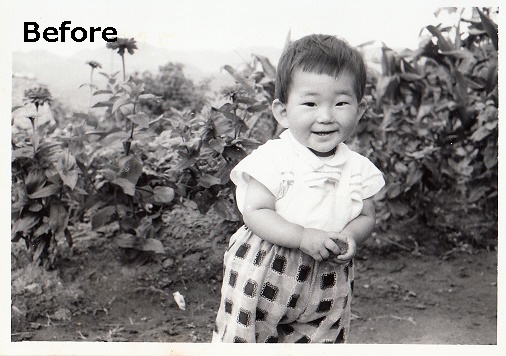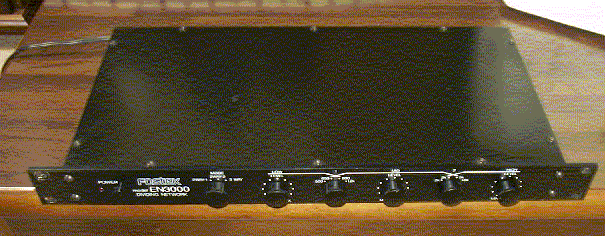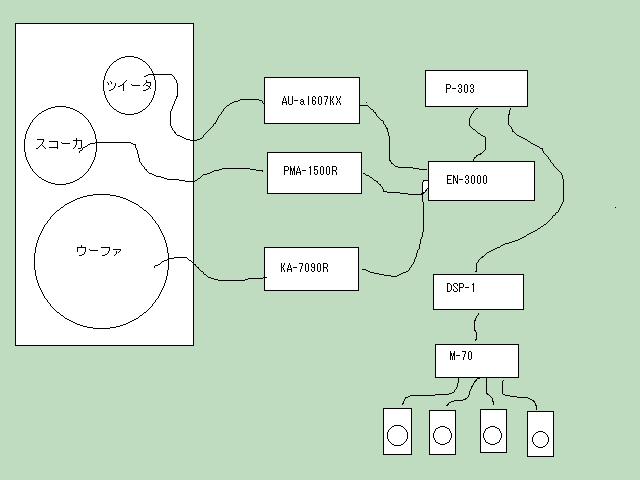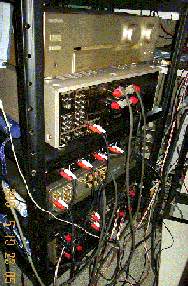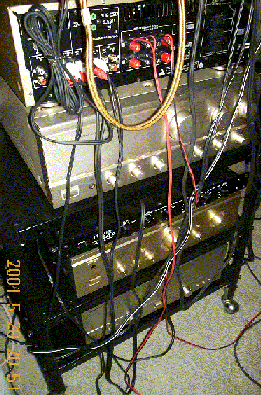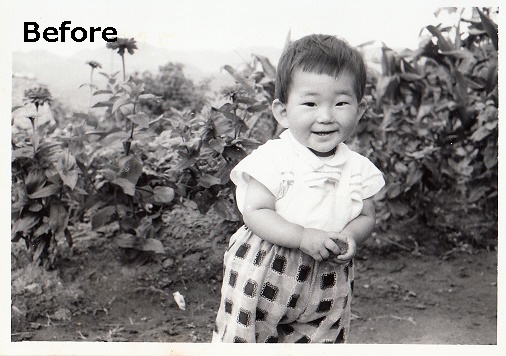

目次
- マルチアンプとは?
- 見たところは、こんなです。
5.1ch(4ch)サラウンドとは、また別のアプローチ
マルチアンプというのは、PAでは、当たり前の手法です。なにしろ、ホールによって音響は当然違うので、あわせ込みやすい。
家庭でも、4chステレオの流行った'70年頃に、「4つもアンプ使うんなら2chでマルチ」というのがありましたし、今でも極限られた高いテレビのスピーカが、そうなっています。
そうでなくても、ネットワークの部品に使ってしまった金額や、一台のアンプで済まそうと無理をした結果を足しこむと、最初からデバイダ買って、マルチにしたほうが、安上がりです。
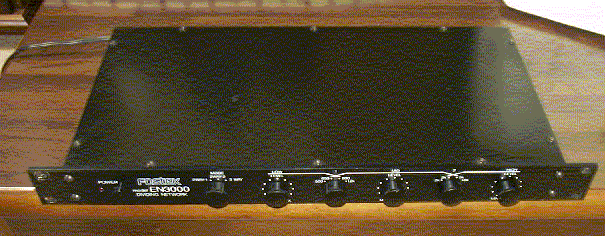

-
<マルチアンプとは?>
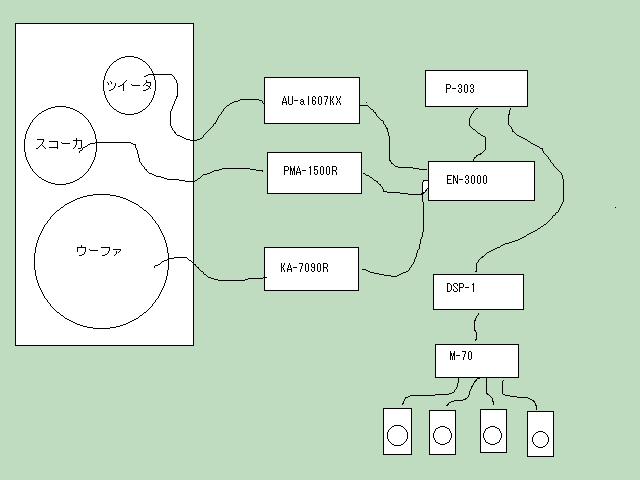
プリアンプ(P-303)の出力を、チャンネルデバイダ(EN3000)に入れて、高い音、低い音、真中の音に分割して、高い音用のスピーカ(NS-690IIツイータ)の繋がったアンプ(AU-a607KX)と、低い音用のスピーカ(RCAウーファ)の繋がったアンプ(KA-7090R)と、真中の音用のスピーカ(NS-690IIスコーカ)の繋がったアンプ(PMA-1500R)に繋ぎます。
5.1chのAVアンプのセットアップに比べれば、すべて直感的に理解できる範疇なので、実に簡単です。
アンプや、スピーカユニットも、担当している範囲が狭くて明確なので、余計なことを考えなくて済むので、再現性が高いです。これが、先に述べた、「PAではあたりまえ」の理由です。
無理に一台のアンプで、すべて解決しようとするよりも、簡単に高いレベルが維持できます。
- <見た目は、こんなです。>
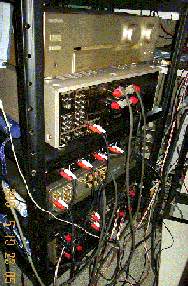
アンプのラックを、前面から見ると、こんな感じです。KA-7090Rはリモコンがついていて、マルチ駆動でないときのアンプとして常用するので、正面を向いています。他は、スピーカの配線がしやすいように、反対を向いています。
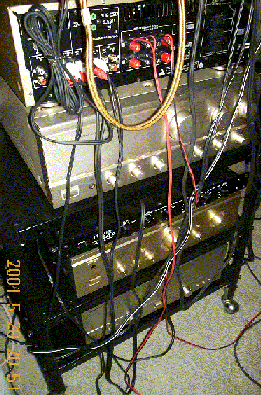
アンプのラックを、背面から見ると、こんな感じです。プリアンプの出力が大きいので、ケーブルは高いものを使う意味がありません。

離れて見えるのは、プリアンプ(P-303)だけですから、普通のステレオにみえる程度です。このプリアンプは、私が知る市販製品の中で、一番操作部分の少ないものなので、すっきりしているとおもいます。
フルレンジのスピーカユニットに1.5μFのコンデンサーだけでツイータ追加しても、箱さえ頑張ればかなり遊べます。しかしながら、もうひとつと思うことがあっても、工夫の余地が限られます。
オーソドックスなウーファとツイータだと、ウーファの上をやはりコイルで落とさないと、ダメで、この時から、泥沼にはまりだします。
ならば、最初から、マルチアンプにしておけば、アンプも選ばなくて済むので楽です。
難しいように見えますが、実は、ウーファから音を出していけば、自然にフラットなセットアップになりますし、スイッチひとつで、位相は直ります。
ネットワークをしまいこんだ箱のL/Cや極性をやり直すというような、悲惨なことが無いだけに、調整はいたって簡単と言えます。
「音楽鑑賞」へ戻る
総目次へ戻る
return
Now JJ0WAJ


平成13年11月29日 de jp3exe ex je2egz