

準備も整い、いよいよ部品のハンダ付け作業の開始です。パソコンデスクに半田ごてと部品を並べ、にわか作業台の出来上がりです。(写真)

最初に発振段の組立てからスタートしました。通常であれば、抵抗やコンデンサからハンダ付けするそうなのですが、今回はトランジスタをハンダ付けしてその周りに部品を取りつけていきました。2SC1815ですので、熱にも静電破壊にも強いので問題は、無いでしょう。
右図が、発振段の部品を取りつけた状態です。

上が部品配置図です。 写真ではR3が見えませんが、チップ部品を使っているからです。灰色の線は、基板のランド同士をブリッジさせているジャンパーです。
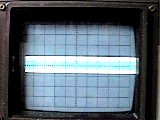 部品を付け終わったら、ミスマウントやハンダ付け部分のチェックをします。 この状態で、電源をつなぎブロックが正常に働いているか確認します。
部品を付け終わったら、ミスマウントやハンダ付け部分のチェックをします。 この状態で、電源をつなぎブロックが正常に働いているか確認します。
オシロスコープでQ1のコレクタの波形を見てみました。私のオシロは、20MHzのオシロなので波形の形までは見ることが出来ませんが、発振していることは確認できました。
ついでに調整もしてしまいましょう。出力に50Ωの抵抗を付けて、基板上の2つのトリマーを回して出力が最大になるように調整します。オシロスコープを持っていない方は、受信機で受信した信号が最大になるように調整をします。

発振は、正常のようなので今度は、3倍オーバートーンで発振しているかの確認です。
カウンターで周波数を測りました。50.6MHzで発振していました。
発振段は、これで完成です。今回は、オシロスコープや周波数カウンターを使いましたが、ハンダ付けと、部品の定数さえ間違わなければ、うまく発振するはずです。
 組み上がった高周波増幅部(基板の右側)
組み上がった高周波増幅部(基板の右側)
本来は、銅箔基板をFCZ基板の下に敷いてバイパスコンデンサー(電源とグラウンド間に入れるコンデンサ)を配線するのですが、今回はFCZ基板上だけで配線しました。
 いよいよ、AF段の組み立てです。トラブルシューティングが行いやすいように別基板で組みました。
いよいよ、AF段の組み立てです。トラブルシューティングが行いやすいように別基板で組みました。
ICは、縦に取付けました。余分な端子はカットして、他と接触しないようにしました。
ICの電源とGNDの間は、220μFのバイパスコンデンサを入れました。
 <C10をQ2のベースに接続。C12をマイクに接続します。>
<C10をQ2のベースに接続。C12をマイクに接続します。>
これで、AFブロックの組み立てが終了しました。
次に確認です。AFブロックのC12にマイクを接続します。電源は6Vの電源であれば乾電池でも安定化電源でもOKです。
次に50MHzのトランシーバーか受信機で50.6MHzを受信します。
 写真<マイクを接続した状態です。>
写真<マイクを接続した状態です。>
私は、IC-726で受信しました。大きな声で喋ると、歪んでしまいますが、変調もきれいにかかっていてまずまずの出来でした。